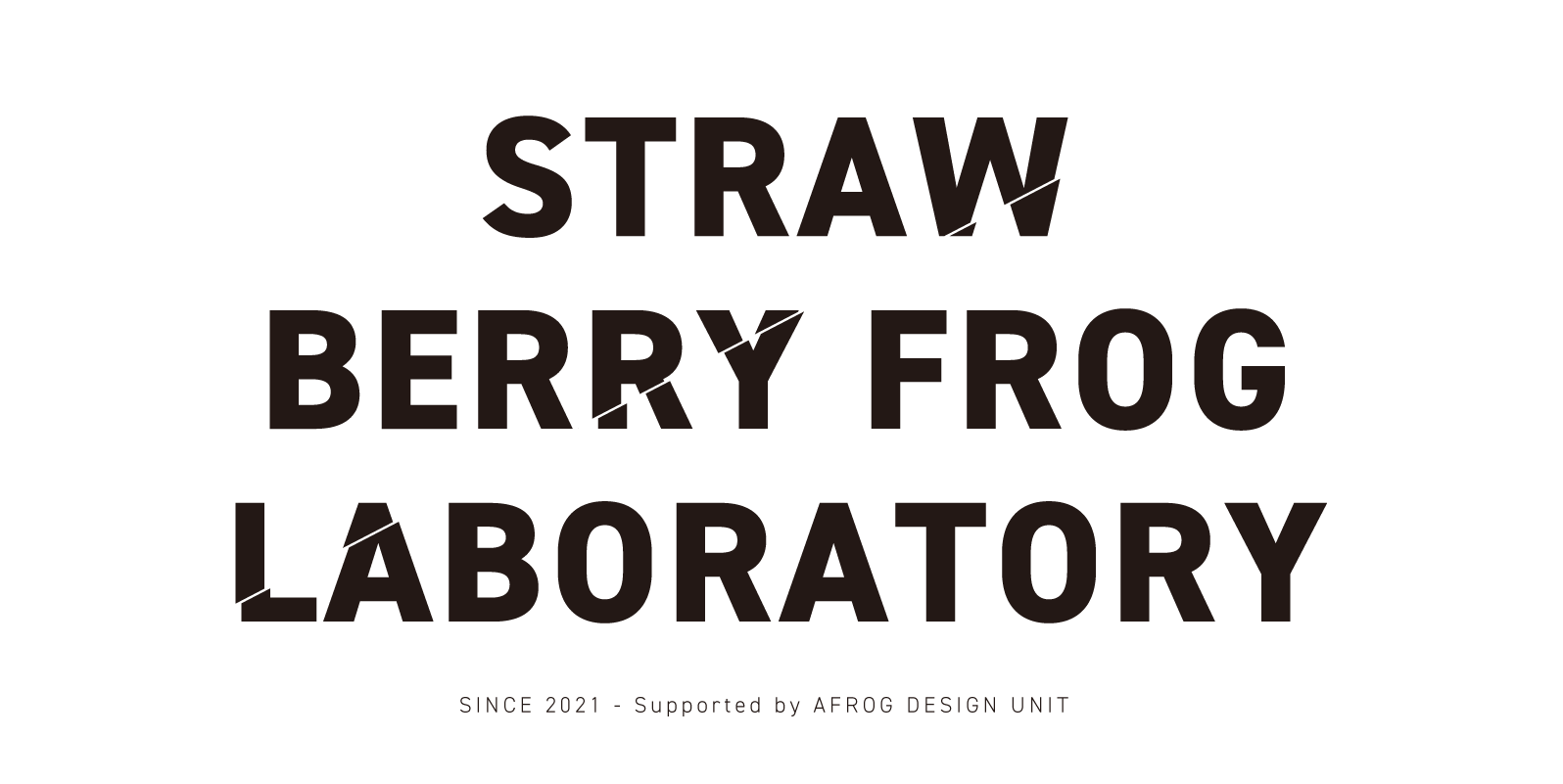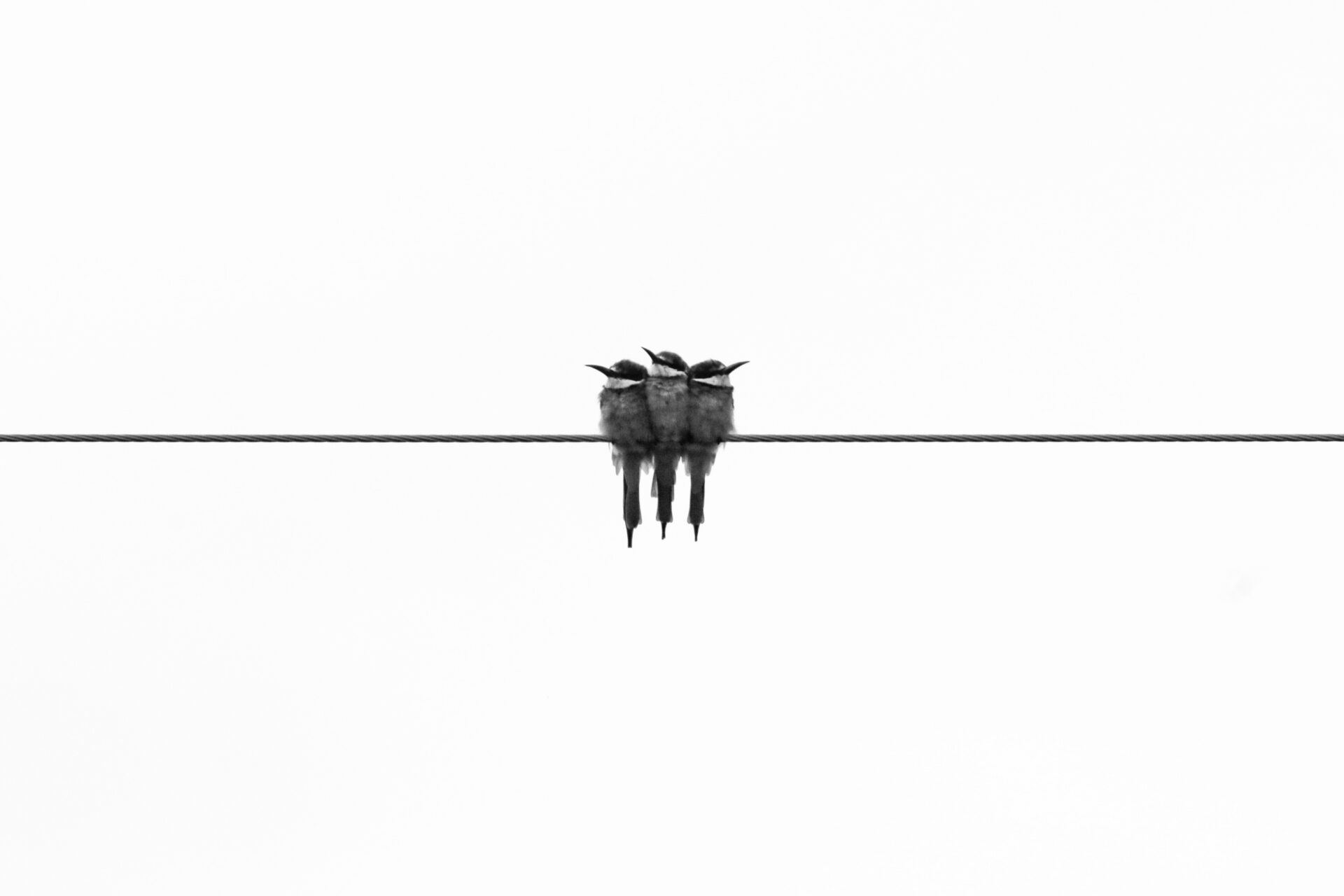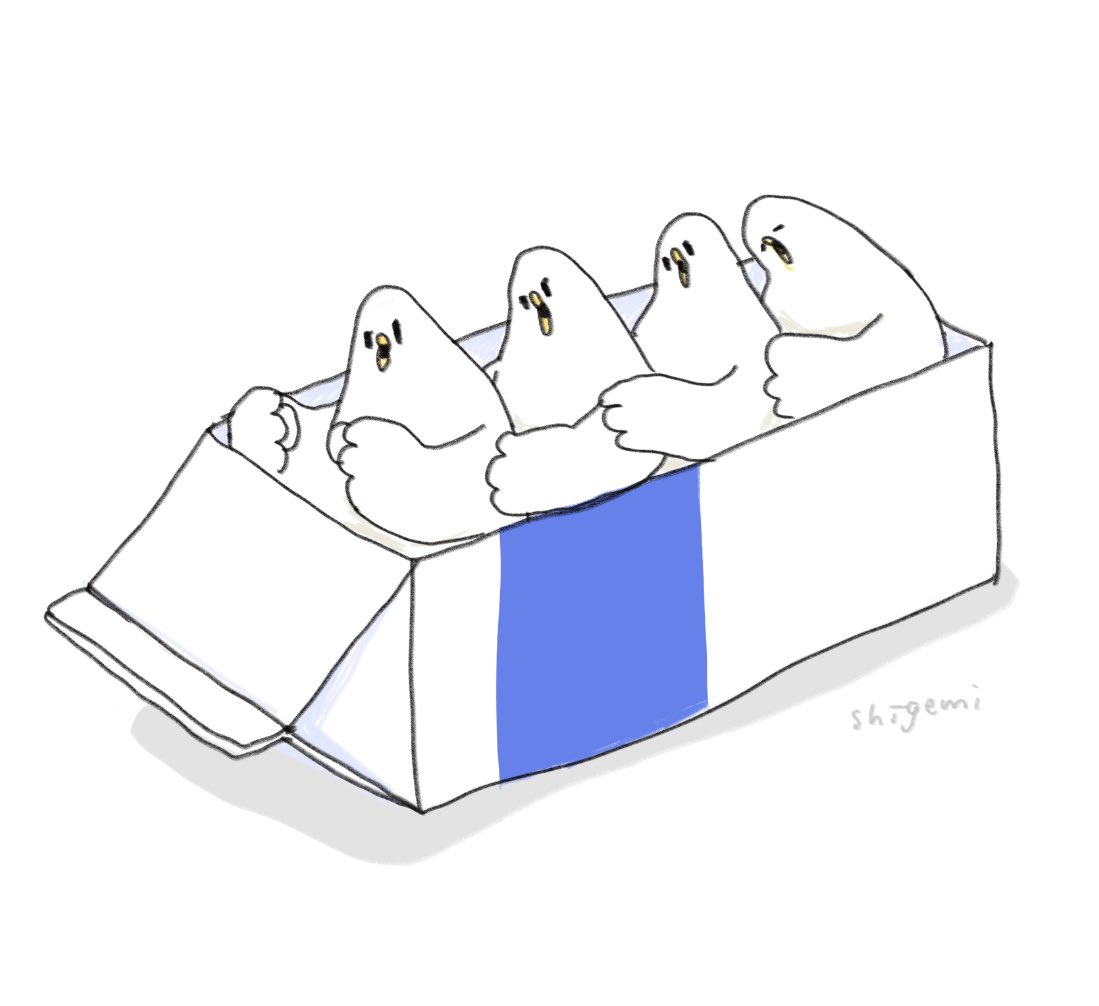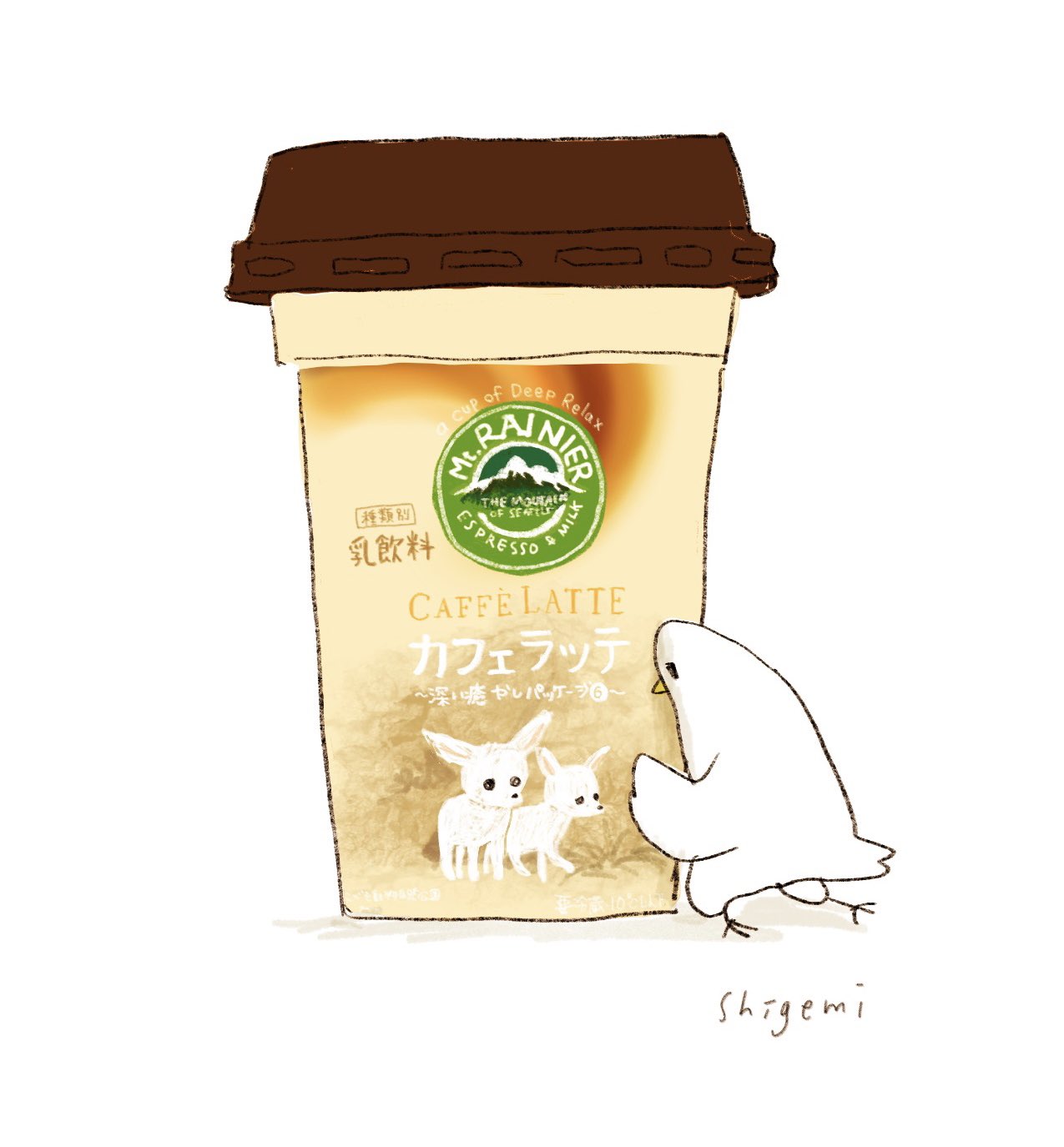「いい人、わるい人」と簡単に人を判断しちゃいますが。そもそも良い悪いってどういう定義?
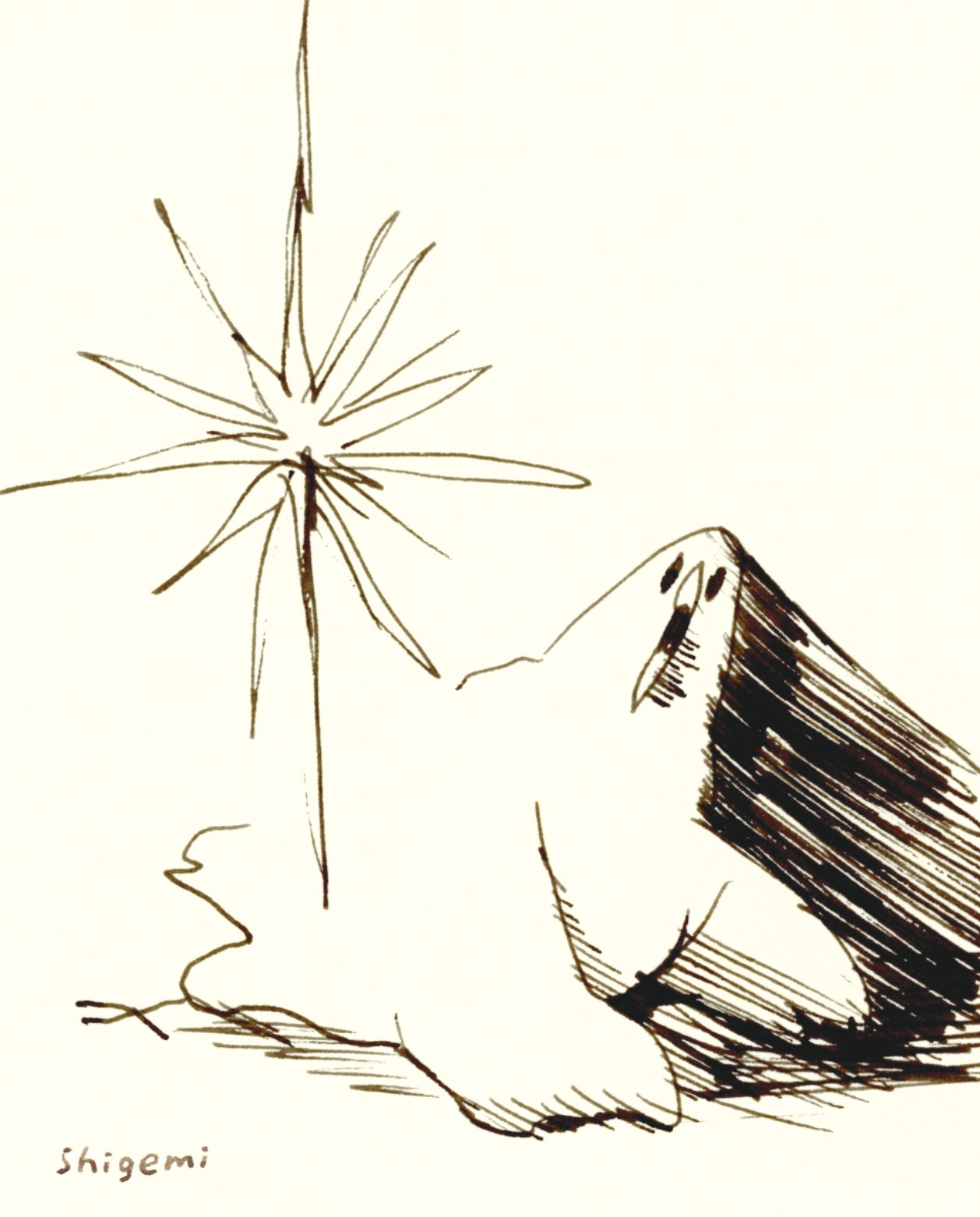
宗教が主流の時代は、良い人、悪い人、には明確に線引がありとてもわかりやすかった。信者なら良い人、未信者なら悪い人。 もし信者で良くない事をする人がいても、神様が許している限り良い人。神が裁いたら、完全に悪い人と確定できた。
こうしたシンプルな分類は「神様がすべてをまるっとお見通しだ!」という信仰心があったから成り立った。そんなに古くない昔、 神様に対する揺るぎない信頼の元、世界は単純に二分化されていたのだ。
しかし、宗教が当たり前ではない時代になって、世界を見ると、良い人、悪い人、を振り分けるのはそもそも不可能じゃ…?と感じる時代になってしまった。
今の時代、よい人、わるい人とは、 単なる個人の主観であり、自分からみて都合の良い行動をとる人を「良い」と感じ、自分からみて都合の悪い行動をとる人を「悪い」と感じる程度のものだと思う。 つまり、良い人や悪い人の定義は、客観的で普遍的なものではなく、主観的で相対的な価値観や倫理観でできている。
洗脳が解け、カルト宗教2世被害者達のぶっちゃけ話を沢山見聞きし、外から現役カルト信者たちを観察すると 「悪い人が多いじゃん…(自分から見て都合の悪い人だらけ)」 とつくづく思うw モラハラ発言、おせっかい発言、ダメ出し発言、人への過度な干渉多すぎ。世では敬遠されがちさんの多さたるや
世で生きづらい人達が集まっても、団体として調和してみえるのはカルト宗教のカルトみの為せる業なのだろう。ブラック企業でも似たような原理をみることができる 多様な背景を持つ人をひとつにまとめる手法として、カルト教育はある意味、人の叡智の結晶なのだろう 経営者として羨ましささえ覚えるw
カルト信者を辞めてから「The 悪い人」に出会ったことが無い。 上司もいない、自分の選択を阻止する権限を持つ人もいない立場だからか、ほぼ全員が良い人にみえる 自分から見て都合が悪い人なんてほぼいない事実に気がつく。 カルト宗教を辞めたら、世界がマジでとても良くなったというお話。
※犯罪者がいないと感じるわけではない。ニュースを見聞きすれば、人に害を加えた犯罪者は実在するし、そこに被害者が存在する事実も理解している。 ここでいう「よい人|悪い人」は、カルト価値観で培った排他的思想を助長するクソみたいなバイアス感覚のことである。
だから直感的に「迷惑だな」と感じることがあるとしても、その人の言動が今の自分にとって都合の悪いことに過ぎないんだな、と考えるようになった。 先日も新幹線の斜め前の席の老婆が何度もケータイの着信音をMAXで鳴り響かせ、大声で話をしていた。「マナーをまもらない迷惑な人だな」と思ったが別に「悪い人」だとは思わなかった。
会話も大声で話すものだから、内容もなんとなく伝わってくる。どうやら親しい誰かが無事乗れたのか?、到着時間は何時だ?とか何度も確認をしているような内容だった。相手も老人の可能性は極めて高い。 着信音が苛つくのは、自分が仕事帰りで疲れているからだ。
ゆっくり考え事をしたいのに音が邪魔でだから鬱陶しいと感じるのだろう。これが外で遊んでいる時なら気にもしない事象だ もし誰かがマナー違反だ!と憤慨でもしようものなら更に煩さが増していたと思う 迷惑行為をする人だとしても、相手は相手の都合で動いているのだ。人の数だけ都合があるww
だからこそルールやマナーがあるのだけども。 自分だって、ルールやマナーなんて破るためにある!というパンクロックな精神が大歓迎の時だってあるのだから何が正義かなんて、その人の都合でなんとでもなる程度のものかもしれないw
「あの人わるい人だ!」なんていきなり断定してしまう時はなにか自分にとって「都合の悪い」事があるのだ。
自分にとって都合の悪いことが、そもそも何なのか少し考えると「自分にとって都合の良いことは何か」を理解できて面白い。
日常的に、相手が いい人 とか わるい人 とか、判断する必要は無いと感じる。もちろん合う合わないは明確に感じるから、もうそれだけでいい。