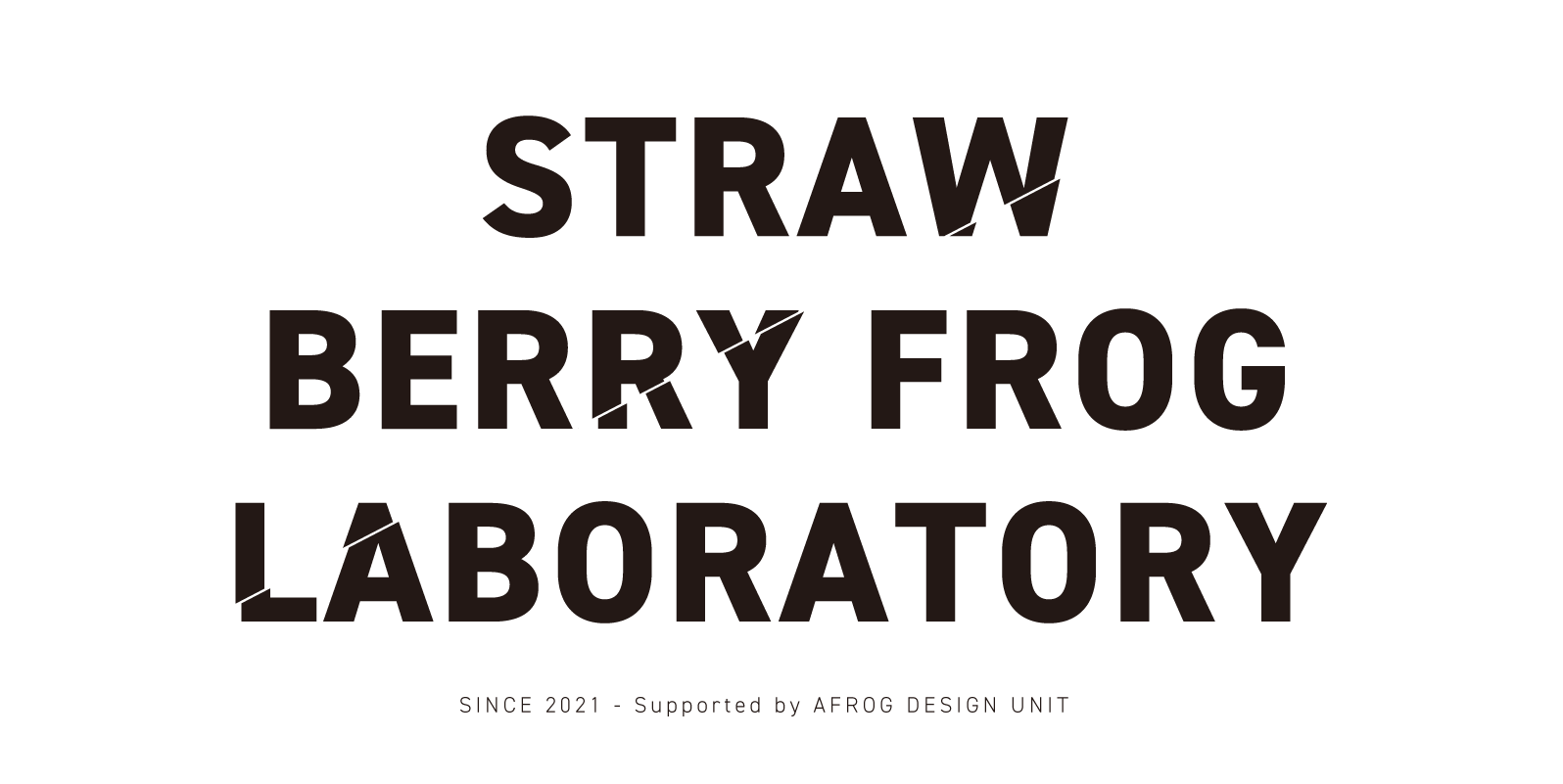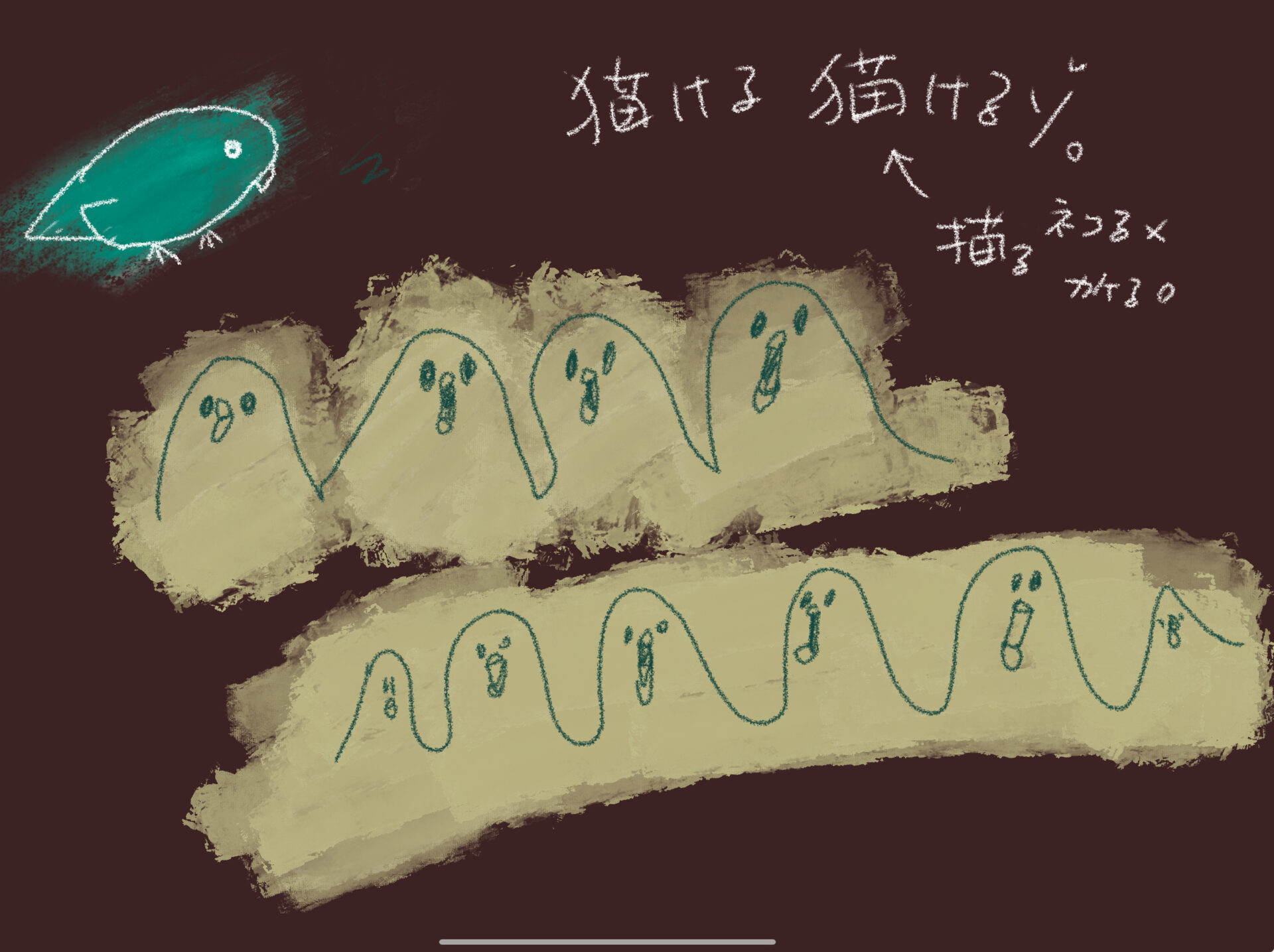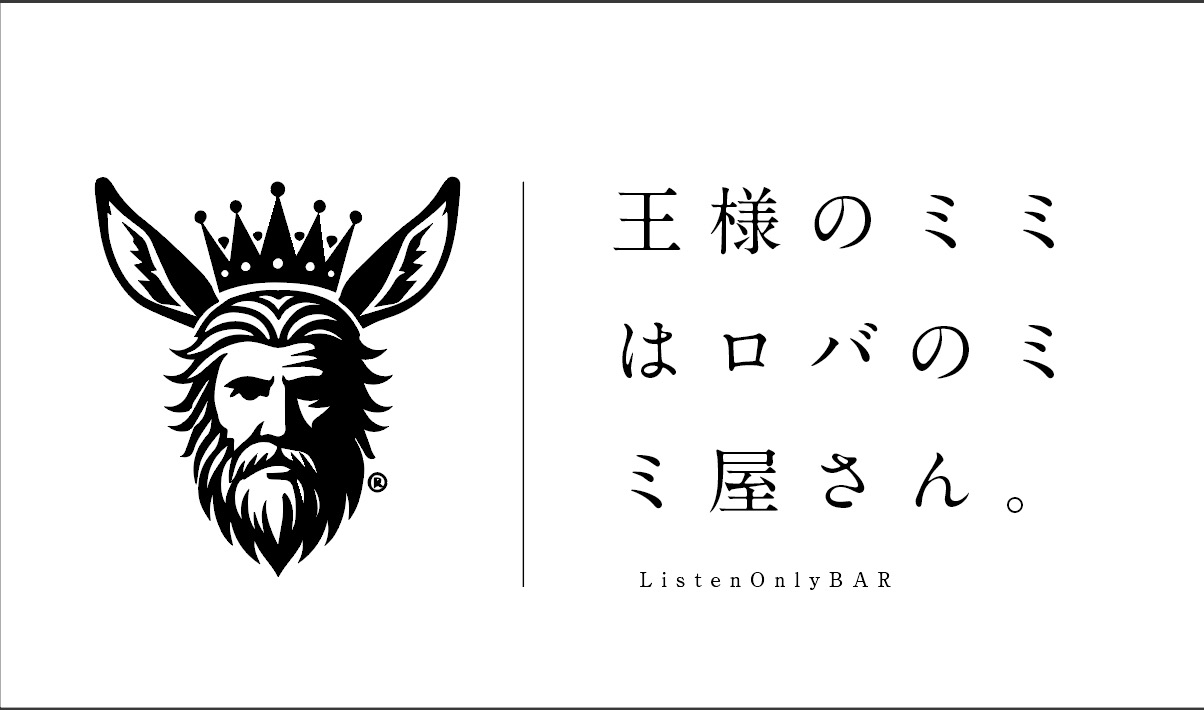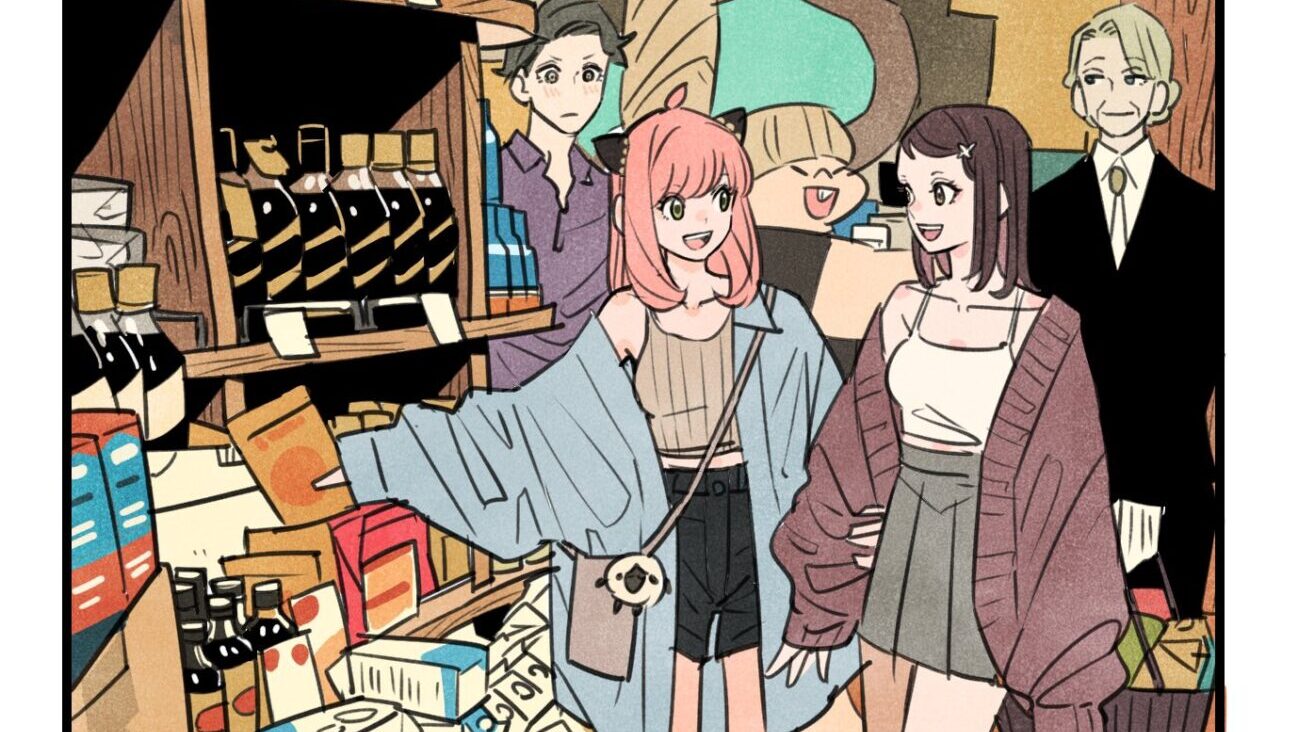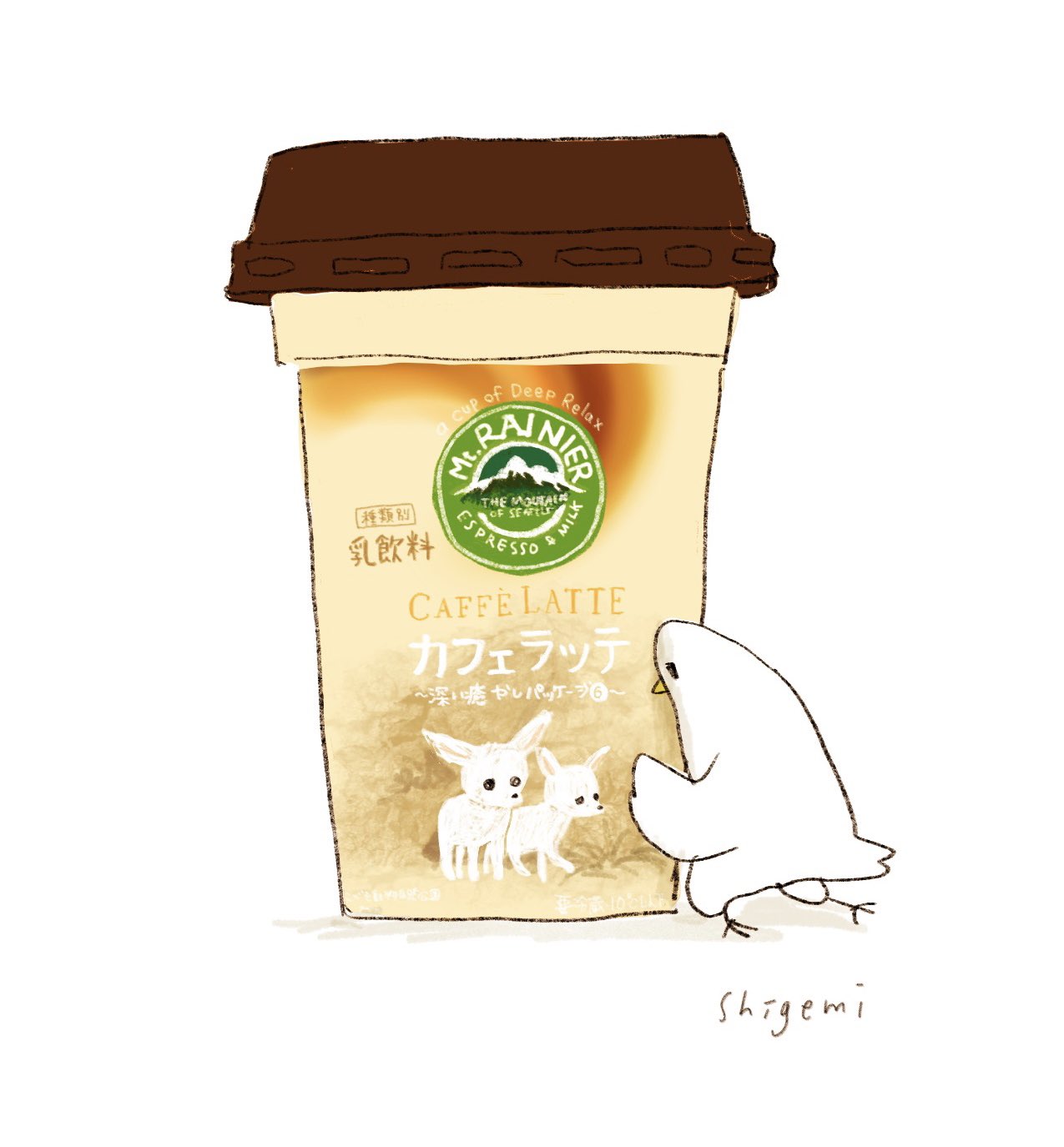そんなバナナ!って古すぎると思うけど。今時の子供が聞いたら逆に新しいんだぜ?
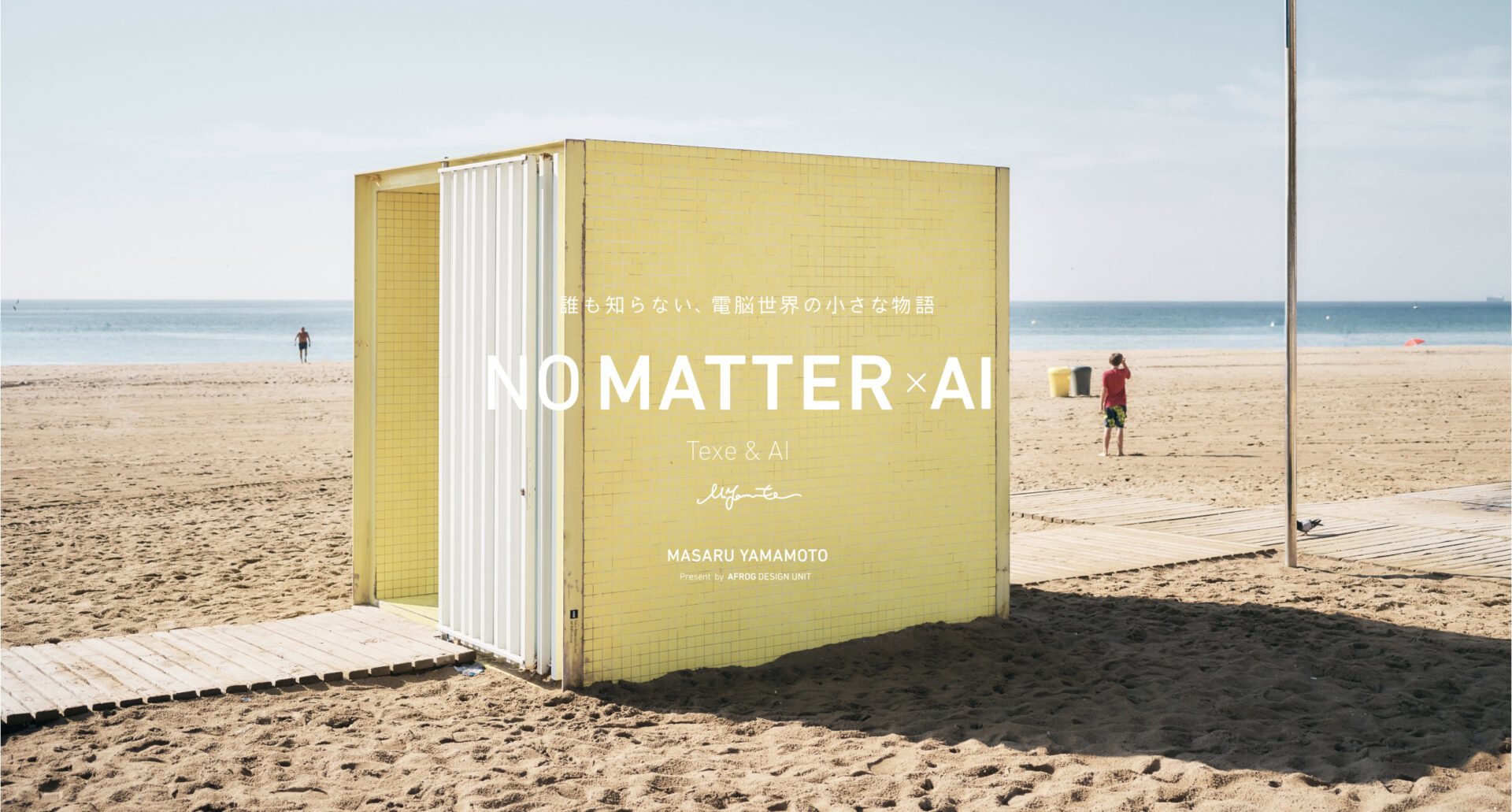
名人とか、大先生とか、天才とか言われている人が、
すっごいものをつくったり、すごいことをしたりするのは、
これはもう当たり前のことのように思われる。
ぼくも、そっちに目がいってたものだ。
ただ、このごろね、名人っていうのは、
「たいしたことない」ものもたくさんつくっていて、
それが「たいしたことない」なりに、
けっこういいんだよねと思うようになったんだ。
けっこういい「たいしたことない」ものを、
ばんばんつくれちゃうのがすごいんだよね。
まず、この話はこれでおしまい。
このごろ、付け焼き刃の「論語」べんきょうをしてるけど、
まぁ、たくさんの解説書やら研究書、啓蒙書があってさ。
そりゃそうだ、もともと「論語」そのものが
孔子の言ったことを解釈したり、
孔子に質問しているという内容なのだから、
すでに「論語」自体が「研究」のはじまりの書だよね。
さらに、それに加えて二千五百年もの間に、
たくさんの人たちの研究が積み重なっているのだから、
付け焼き刃で読んでいても、とても追いつかない。
それでも、どれがじぶんにフィットする考えかなとか、
不勉強なりに思うようにもなるんだ。
で、最初は渋沢栄一の書いた
『論語の読み方』という本を、
ちょっと距離をおいて読んだりしていたんだ。
他の学者や研究者や作家たちとちがって、
渋沢栄一は実業の人、つまりは実利を重んじる人だからね。
『論語と算盤』という本も書いているくらいで、
自らを利するために「論語」を使っていると想像してた。
ところが、あるとき、気づいたんだよね。
渋沢栄一だけが「論語」を「使っている」のだけれど、
他の人たちは「研究」しているんだなと、ね。
もともと孔子は、「わたしの言うことを研究しろ」と
言っていたわけじゃなかったはずだ。
「使ってもらえる」ことを望んでいたと思うし、
わたしの考えは「使える」ものだという自負もあった。
だとしたら、さんざん「論語」を使って生きて、
使うものとしての「論語」を語っている渋沢栄一こそ、
『論語の読み方』を書くには最も相応しいのではないか。
わたくしも、そう思うようになったのであります。
今日も、「ほぼ日」に来てくれてありがとうございます。
「自己啓発本」の最初の源泉は、考えてみたら「論語」だ。